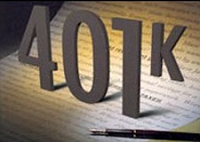確定拠出(401k)制度と個人貯蓄
確定拠出制度の目的は、高齢期における所得の確保にかかわる自主的な努力への”支援”です。
国が行なう支援とは、積立をする掛金と運用益に対する”課税負担を優遇”することです。
課税負担が優遇されることによって、課税の適用を受ける個人貯蓄と比べて有利に積立額を増やすことができます。
特に、高齢期における確定拠出の運用メリットについては大変顕著であります。
日本版401Kによる個人資産は、60歳まで引き出すことができませんが、一方で、70歳まで制度の利用をすることができます。資産運用は、資産全体に対して行ないますので、例えば、60歳時の個人資産合計が3542万円あったとすると、その8%の運用収益は約283万円(年率計算)となります。仮に個人貯蓄に同じ3542万円の個人資産があり、同じように8%の運用収益を上げたとしても20%の利子課税が課せられますので、運用収益は約226万円にとなり、差額は57万円になります。60歳以降も70歳まで確定拠出制度を利用した場合、個人貯蓄と比べたこの運用益の差額は、加速度的に大きくなります。
高齢期における確定拠出制度のこの大きな運用メリットを受けるために、個人貯蓄の資産を確定拠出制度の中に一括して移行することは認められていません。毎月の拠出限度額の範囲内で資産を構築する方法だけが認められています。
高齢期においても安定した資産の分配(確定拠出による年金収入)を受けながら生活を送るためには、できるだけ早い時期から、現役時代の給与課税メリットと運用益メリットの優遇も受けながら、毎月の拠出限度額の範囲内で確定拠出制度の中で少しずつでも資産を構築していくことだと言えます。

 HOME
HOME